3月30日に世界最高峰のEV(電気自動車)レース「ABB FIAフォーミュラE選手権第5戦」東京E-Prixがお台場で開催された。2014年にシリーズが始まり、2020年からFIA(世界自動車連盟)の世界選手権シリーズとなり、年々人気が高まっている。ちなみに「フォーミュラ」とは、F1と同じように、タイヤが露出した競技専用1人乗りマシンで競われることを示している。

「フォーミュラE」は、これまでのレーシングカーと根本的に異なるのが、エンジンの代わりにモーターを使っている点だ。エンジンからの爆音ノイズや排ガスを一切出さないことから、ニューヨーク、香港、リオデジャネイロなど世界の大都市で開催され、公道を封鎖して行なわれる。
自動車レースの概念を変える「フォーミュラE」
街中でレースを行なってもうるさいと言われることはないし、空気も汚れないのがこれまで行われてきた自動車レースとの大きな違いだ。都市部で開催されることが多いので、地下鉄やバスなどの公共交通機関を利用して、気軽に観戦に行けるところも新しい。「フォーミュラE」は、マシンや競技規則が新しいというだけではなく、自動車レースのあり方や観戦方法についても大きく概念を変えたのだ。

今回、日本で初めて開催された東京E-Prixでは、ワークスチームとして2016年から参戦し続けているジャガーTCSレーシングが、参戦から100レースを迎えた。チームに所属する2人のドライバー、ミッチ・エバンスとニック・キャシディは、午前中に行なわれた予選の結果、決勝レースで9番と19番グリッドを確保した。ちなみに「フォーミュラE」の場合、予選の戦い方もF1など従来の自動車レースとは大きな違いがある。全車が一斉にコース上でタイムを競うのではなく、準々決勝、準決勝、決勝と、4台あるいは2台ずつがコースインして、そのタイム差で順位を決めるという勝ち抜き方式が採用されているのだ。観客にとっては勝ち負けがわかりやすく、予選の最後のレースまで眼が離せない状況が続くため、エキサイティングで面白い。

決勝は、1周2.582kmの特設コースを35周する形で行なわれた。鈴鹿サーキットや富士スピードウェイと較べれば、コース幅は狭く、全長も短い。ほぼフラットな駐車場と公道にコースが設営され、スタンドが建てられるため、コース全体を眺められるところがない。しかし、巨大なスクリーンが会場内のあちこちに設けられているため、レースの展開はどこからでも十分に把握できるし、観客への情報提供量も豊富だ。このあたりにも、新しい都市型モータースポーツの息吹を感じる。
決勝レースは、実にスリリングだった。スタートからテール・トゥ・ノーズでの接近戦が続き、わずかなきっかけで追い越し、追い越されて順位が目まぐるしく入れ替わってしまう。かといって、思慮なく仕掛けていけばいいというものでもないのは、バッテリーに蓄えられた電気のパワーをできるだけ効率良く使わなければならないからだ。

走行ラインや空気抵抗などの微細な変化によっても、電力の消費量は変化してしまう。チームスタッフの綿密な戦略と併せて、ドライバーにきめ細かなエネルギーマネジメントが求められるのが「フォーミュラE」というレースの難しいところであり、醍醐味のひとつとなっている。

ジャガーTCSレーシングの東京E-Prixは、ニック・キャシディが19番スタートから8位でフィニッシュ。ミッチ・エバンスは15位。チーム代表のジェームズ・バークレー氏はレース後、次のようなメッセージを残した。
「応援ありがとうございました。チームが望んだ結果とはなりませんでしたが、ニックはオーバーテイクが難しいコースで素晴らしい奮闘とスピリットを見せてくれました。ジャガーTCSレーシングはチームランキングで首位をキープしており、ニックは首位から2ポイント差の2位、ミッチが6位に着けています。次のイタリアGPではチームがさらなる健闘を見せてくれるでしょう」
主催者によると入場者数は2万人。好天にも恵まれ、日本初の公道EVレース、東京E-Prixは成功に終わった。スタート前は、どんなレースになるのか、まったく見当もつかなかったが、終わってみれば新しい時代の新しい自動車レースであることを見事に示していたように感じた。エキゾーストサウンドも、マシンから排出されるガスのにおいもなく、幅の狭い短いコースを知的に攻略できた者が勝利をつかみ取る。
そして、観客を飽きさせない様々な演出も功を奏していたように思う。従来型の自動車レースと今後しばらく共存していくのだろうが、これまでのイメージを一新する、まったく別の魅力を感じさせてくれる新時代のモータースポーツだった。
ジャガーが掲げるREIMAGINE戦略とは
ジャガーTCSレーシングは、続く第6戦、第7戦と連続でポイントを獲得。第7戦では表彰台に上がるなど、チーム・ランキングで首位をキープし、今季好調を維持している。じつは「フォーミュラE」への参戦と併せて、ジャガーは野心的なプロジェクトを推進しているのをご存じだろうか。それが2021年2月に発表された「REIMAGINE」戦略だ。REIMAGINE戦略とは、ジャガー・ランドローバーの新しいグローバル戦略であり「サステナビリティに富んだモダンラグジュアリーの再構築、ユニークなカスタマー・エクスペリエンスの提供、ポジティブな社会的インパクトの創出を目指す」としている。

具体的には、
・2039年までに排出ガスを実質ゼロにする
・ジャガーを2025年からピュアEV(電気自動車)のラグジュアリーブランドとして再生する
・2030年末までにジャガー・ランドローバーブランドの全モデルにピュアEVの選択肢を設定する
などなど、他にいくつも掲げられたのだが、我々が最も気になるのが2025年からジャガーはEV専業ブランドになるということだ。ジャガーはすでに「I-PACE」というEVを製造・販売しているが、「F-TYPE」のようなスポーツカー、「XE」や「XF」「XJ」のような4ドアサルーン、「E-PACE」や「F-PACE」のようなSUVなど、多種多様なエンジン車も造っている。ところが、これらの生産を終了し、新しいEVだけでジャガーのラインアップを再構築して編成するというのだ。

この発表を聞かされた時は本当に驚いた。なぜなら、ジャガーの現行モデルはいずれも魅力的で、急いで生産を止める理由が思い当たらなかったからだ。もちろん、自動車メーカーとして生き残るためにEVへの移行は必然かもしれないが、それは「段階的」に行なわれてもかまわないはず。この方針が発表されたのが、2021年2月だから、2025年まではまだ4年あったはずだ。しかし、2024年の今となってはもう来年のことでもある。はたして、REIMAGINE戦略は発表当時の予定通り、実行されるのだろうか。
ジャガー・ランドローバー・ジャパンのジャガートランスフォーメーションディレクターであるサミュエル・ゴールドスミス氏に話を聞いた。

「REIMAGINE戦略に変わりはありません。発表した時と変わらず、着々と準備が進んでいます。ジャガーはプレミアムEVの専業メーカーとして再定義され、再出発するのです」
それにしても、2025年からすべてのジャガーをEVにするというのはあまりに大胆な戦略だといえる。この発想はどうやって生まれたのだろうか? 同社代表取締役社長のマグナス・ハンソン氏に尋ねた。

「我々のクルマづくりを高く評価していただけるのは光栄なことですが、一方で会社の財務面を強化する必要にも迫られていました。サステナビリティやゼロエミッションを実現するためです」
では、どのようなEVの製造を目指し、開発を行なっているのだろうか?
「3つの要件があります。1つ目がモダンラグジュアリーであること。ジャガーは長い伝統を有するブランドですが、それをそのままなぞって発展させるのではなく、現代的なラグジュアリーとして解釈し直して新しいクルマを造ります。2つ目は、プラグインハイブリッドなどではなく、完全なEVを開発すること。そして最後、3つ目は、そのEVが革新的で他のクルマとは全く異なっていることです」(ゴールドスミス氏)

現在、開発は3つのデザインチームによって行なわれており、17台のプロトタイプが製作されたことも明かしてくれた。すでに、2025年に発表される最初のEVが4ドアGTであることも発表されている。
「デザインコンセプトは、2024年末に発表する予定です」(ゴールドスミス氏)
その4ドアGTの後、全く別のEVが2台投入される予定だという。いったい、どんな2台が登場するのか訊いてみた。
「まだ明らかにできず“楽しみにしていてください”としか言えないのが残念です(笑)。ただひとつ言えるのは、2台目と3台目はGTでもなく、サルーンでもないということです」(ゴールドスミス氏)
ただ、販売価格帯は決まっており、1台10万ポンド(約1900万円)以上だという。超高級車のゾーンだ。
「我々は台数をたくさん造ることより、独創性があることを優先したいと考えていますので、まずは最初の3台に注力していきます」(ゴールドスミス氏)
最後にハンソン氏が付け加えた。

「現在、マーケットに出回っているメインストリームのEVとは完全に違ったものになります。ジャガーの原点に立ち返りながら、モダンで前例のないユニークなクルマとなるでしょう。これにより、ジャガーは感性に訴えかけるデザインと次世代を切り開くテクノロジーを備え、非常に美しく、新たなポートフォリオを提供するピュアEVのラグジュアリーブランドとして生まれ変わります。デザインのインスピレーションを自動車からではなく、現代の高級家具や建築などから導いているところも、これまでのクルマには見られなかった特徴です。ご期待ください」

2人の説明を聞いて、2025年に登場する4ドアGTのEVの姿を即座にイメージすることは難しい。逆に言えば、簡単にイメージできるようなものは、最初から目指しているわけではないとも受け取れる。過去にデザインソースをもつような既視感を感じさせないものになるはずだ。
ジャガーといえば、誰もが認める偉大な栄光を背景にしている自動車メーカーだ。ルマン24時間レース連覇をはじめとする、数多くのモータースポーツでの勝利、「Cタイプ」や「Dタイプ」あるいは「Eタイプ」の美しさ、スポーツカー並みの動力性能を誇るサルーン、イギリスの伝統に裏打ちされたクラフトマンシップなど、数えればキリがない。
ところが、あえて「ブランド価値や資産を有効活用する」などとお決まりの方法論を選択せず、オリジナリティーを追求しながら高みを目指し、ブランドを再定義するというのだ。エンジン車の時代の延長線上にではなく、新たに次元を1つや2つも上げたところからスタートする、モダンでラグジュアリーなEVが生み出されるのかと想像するだけでワクワクする。
「すでに『XJ』は製造を止めていて、現行の『XE』や『XF』は2024年中に製造が終了します。『F-TYPE』や『E-PACE』『F-PACE』などもそれに続き、2025年にかけて最終モデルが限定発売されますので、ご予約はお早めにお願いします」(ゴールドスミス氏)

ジャガーらしさを体感できる「I-PACE」の魅力
先述の通り、ジャガー初のEV「I-PACE」は2018年に発表された。2024年モデルではマイナーチェンジが施され、フロントグリルとウインドモールの形状が変わり、タイヤも22インチに拡大した。前後に1基ずつ計2基のモーターによって4輪を駆動し、最高出力は400馬力を誇る。先日、最新の「I-PACE」に試乗することができたので、参考までにインプレッションをお届けしたい。場所は、富士スピードウェイのショートコースだ。

「I-PACE」の独特のエクステリアデザインは見慣れるということがなく、個性的なアピアランスに思わず、不思議と見惚れてしまうところがある。コースに入って走り始めると、走り出しの力強い加速とその滑らかさに感心させられる。エンジン車だと、エンジン回転が上がってからでないと加速力が伴わないが、EVはモーターで走るので立ち上がりから鋭く加速していく。それは一般公道でも変わらないが、サーキットだと余計にそのメリットを強く感じる。

減速時もEVはモーター回生も使うのでコースを走りやすい。フットブレーキを踏み、ブレーキディスクがパッドに締めつけられるのと同時に、モーターに抵抗を与えて回生を生じさせ、電気を回収することが減速にもなっている。

「I-PACE」はバッテリーを床下に設置していることもあって、減速時やコーナリング時の安定感が高い。また、エンジン車でサーキットを走ると減速時は大きく前のめりになりがちだが、「I-PACE」は車体全体が沈み込む感じが強く、ボディーの上半分が前後左右に大きく揺れ動かされることも少ない。そうした特性は一般道でも感じることが多く、理解していたつもりだったが、サーキットを走るとさらに顕著に感じる。EVの運動性能の長所を、サーキット走行によって改めて気づかされた。
もうひとつ、EVの運動性能の長所を体感させられたことがある。それは、各種の電子制御による不自然な挙動が感じられにくいことと、感じてもそれがナチュラルなものだということだ。例えば、エンジン車で減速した後にコーナーをクリアし、そこから加速させようとするとエンジン制御によって減じられたエンジンパワーとクルマのスピードがシンクロせず、思う通りのタイミングで加速できなかったりする。エンジン制御がデジタルで行なわれているのに対して、エンジンからの加速力はアナログであり、エンジンの各パーツを動かしていることによる遅れや制御のし過ぎなどが原因だからだろう。

しかし、EVの「I-PACE」ではそのもどかしさがほとんど感じられない。エンジンと同じようにか、それ以上にモーターにも制御が施されているのだが、その制御がクルマの動きにピタリと合っていて齟齬をきたしていない。エンジン車と比べると、とても自然に制御が行なわれている。運転操作の至らなかったところを、ドライバーには感じさせずに瞬時に制御を行なってフォローしてくれる感じだ。サーキットでは体感できたが、公道で体感することは稀だろう。加速の鋭さや滑らかな走りだけがEVの運動性能の長所ではなく、姿勢変化の少なさや制御の自然な働きも大きな魅力であることに気づかされた。

ジャガーは2018年に電動SUV「I-PACE」を発売し、いち早くEVを世に送り出した。しかし、EVは他メーカーからも続々と投入されており、競争は激化している。そんな中、このREIMAGINE戦略によって、全く新しいジャガーのEVがどんなクルマに仕上がってくるのか、楽しみでしょうがない。
■関連情報
ジャガー「I-PACE」公式サイト
取材・文/金子浩久(モータージャーナリスト) 撮影(人物・車両)/望月浩彦 写真提供(レース関連)/ジャガー・ランドローバー・ジャパン
Recommended






Ranking
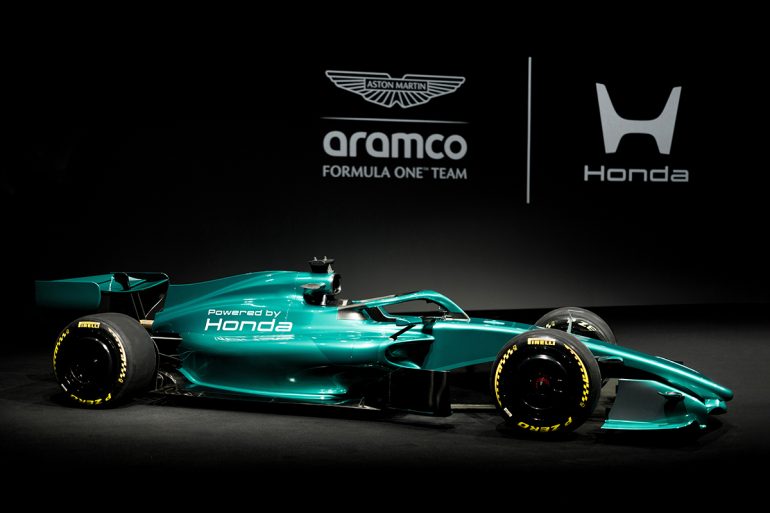




Brands
Alpine

BMW

Lexus

Audi

Aston Martin

Cadillac

Chevrolet

Jaguar

Ferrari

Bentley

Porsche

McLaren

Maserati

Mercedes-benz

Landrover

Lamborghini

Lotus

Rolls-royce









