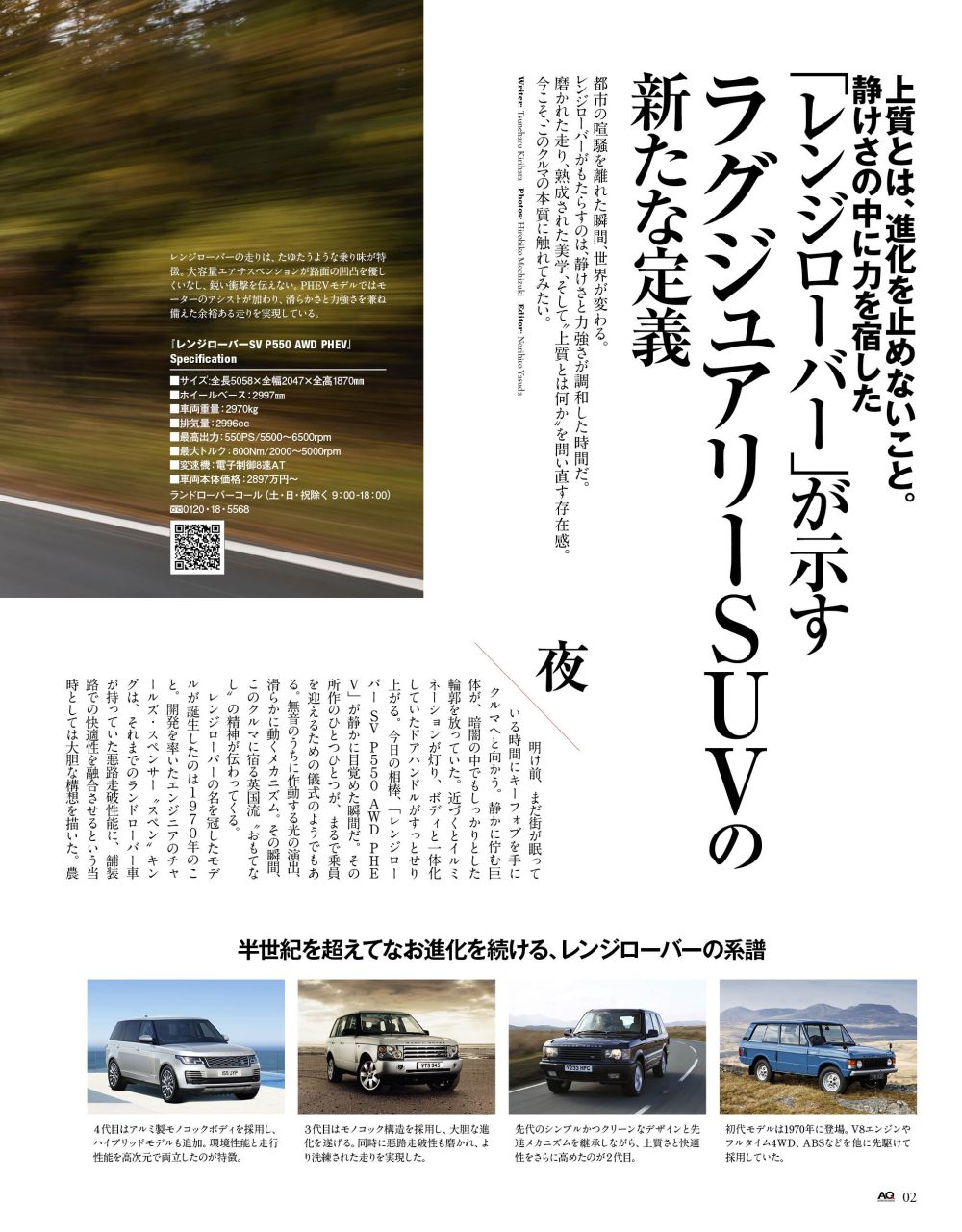アルピーヌ・ブランドの復活とともに新生「A110」が僕らの前に正式に姿を現したのは、初代の生産終了から40年が経った2017年のジュネーブ・ショーだった。あのときの興奮はいまでも忘れることができない。ボディサイズも違えばドライブトレインのレイアウトも異なるというのに、どこからどうみてもそれは僕らがよく知るかつての「A110」だった。

縦置きリアエンジン、リア駆動から横置きのミドシップに変わっても、重量物を中心に置いて運動性能を上げるという点でネガティブなものはなにもない。アンダーパネルが生み出すダウンフォースで必要にして十分なトラクション性能を確保するという、まるでレーシングカーに用いるような方法は、再現したオリジナル「A110」のエレガントなフォルムの純度を高めるために必要な手段でもあった。

なによりも共感したのは、そのコンパクトなボディと2リッターに満たない4気筒エンジンだ。600馬力を超えるスーパースポーツカーが登場しているいまの時代に、あえて小さなエンジンの小さなスポーツカーを登場させたのは、アルピーヌに「Light is right(軽さは正義)」という創業当時から続くスポーツカーづくりの哲学があったからだ。その軽さがもたらすこれぞライトウェイトスポーツという一体感のある走りは衝撃的だった。あえて低められたグリップ性能を喜びとして堪能できるように仕立てられたチューニングは見事というほかなく、ただひたすら箱根のワインディングを走り続けたときのことはいまでもはっきりと覚えている。

そんな現行型アルピーヌ「A110」の試乗会が長野県の車山高原で行われた。アルピーヌとしてはこれが内燃エンジンを搭載する最終モデルの試乗会となる。アルピーヌの社名がアルプスのワインディングに由来することはよく知られている。つまり最後の試乗会を山岳ワインディングで締めくくろうというわけだ。最後の試乗車として用意されていたのは「A110アニバーサリー」と「A110GTS」、そして「A110 R70」の3台。朝の柔らかな光があたりを薄っすらと赤く染めるなか、最初に試乗したのはフラッグシップモデルの「A110 R70」だ。

ベースは「A110R」で、300馬力の最高出力と340Nmの最大トルクに変更はない。「R」と異なるのはブランドの創立70周年を記念するロゴがフェンダーやシートのヘッドレストにつくくらいだろう。「R」モデルに乗るのは初めてだったが、まず驚いたのはそのダイレクトな感触だった。


これは一体感があるというどころの話ではない。まるでステアリングとタイヤが直結しているような反応の素早さだ。そう感じるのはクッションの薄いバケットシートの効果もあるからだろう。しかも身体は4点式のレーシングハーネスでしっかり固定されている。

こうなると身体はボディの動きに合わせて激しく上下に揺すられるのが普通だろう。悪くすれば気分が悪くなることもある。それがどうだ。「R70」の一体感には不快なところがない。アクセルのオン・オフでもブレーキングでも、クルマの姿勢や荷重移動が手に取るようにわかる。しかもその伝達される情報のなんとクリアなことか。

路面の悪いところではもちろん衝撃もある。それがコーナリング中だとバンッと瞬間的に横に飛ぶこともあった。そんなときでも冷静に判断して瞬時に対処できるのは、ドライブする側がクルマとしっかり対話できているからだろう。それを可能にしているのはボンネットやルーフ、リアのエンジンフードなどをカーボンにして軽量化しているからに違いない。「R70」の車重はたったの1090kgだ。車重が軽ければ必要以上にダンパーも固めなくてもすむ。乗り心地がハードでも不快にならない。それにはカーボンのホイールも貢献しているはずだ。


長く過酷なラリーコースを攻め続けても、最後までドライバーが冷静にコントロールできるのがラリーカーだが、そういう意味で「R70」はラリーカーの要素をすべて備えていると思った。

そんな「R70」の次に試乗した「A110アニバーサリー」は、「A110」のラインアップの中では「R」モデルの対極にあるモデルと言っていいだろう。アニバーサリーとあるが、性能的には素の「A110」にあたるのがこのモデルだ。「R70」と「GTS」は300馬力だが、アニバーサリーはチューンの異なる252馬力のエンジンを搭載する。アニバーサリーの特徴は、一言で言えばしなやかなことだろう。性格は「R70」とはガラリと変わってGT色が強くなる。「R70」と同じコースのビーナスラインを走ったが、身体への負担は格段に少ない。

では「アニバーサリー」との対話が面白くないのかと言えば、そんなことはまったくない。「R70」の楽しみ方は4点式ハーネスとスペシャルなフルバケットのシートが示すとおり、本来なら最適な場所はサーキットだろう。車庫で眠っている時間が長くなることも容易に想像できる。一方、アニバーサリーは毎日でも乗ることができるスポーツカーだ。ドライバーを包み込むような低く構えた小さなボディはエレガントで美しく、オーナーの満足度も高いはずだ。現行の「A110」の開発にかかわったデザイナーは、攻撃的ではなくエレガントであること、そして時間の経過に流されないタイムレスな存在であることを目指したと言う。これは所有する喜びにつながるはずだ。

さらにもうひとつ付け加えると、車両開発のエンジニアは望外なパワーは必要なく、200馬力程度でも十分に楽しめるスポーツカーが目標だったと言っている。つまり、「A110」でアルピーヌ・ブランドを復活させた熱い思いを持つエンジニアたちの理想は、この素のモデルである「アニバーサリー」だというわけだ。ビーナスラインでの「アニバーサリー」との対話は、それは楽しいものだった。思い通りにクルマがコントロールできる喜び。寸止めの効いたチューニングはスポーツドライビングのスリルを手の内で楽しませてくれる。252馬力だからこそ享受できる世界があることを、この「A110アニバーサリー」は教えてくれている。

「A110」で楽しむ世界。今回の試乗会で本当にその世界を垣間見ることができたのは、最後に乗った「GTS」のときだった。試乗コースとして選んだのは「R70」と「アニバーサリー」のときとは違う、一番遠いコースだ。それは高原の尾根筋を行くビーナスラインから外れた脇道で、交通量の少ない長いワインディングだった。メインルートから外れた途端、道の雰囲気が変わった。尾根から一気につづらおりの下りが始まる。もう朝の冷え込みが厳しくなっているのだろう。凍結防止の融雪剤が撒かれたコーナーでは、ズルッとリアが滑る。こういうときでもコントロールしやすいのが「A110」だ。下りきるとこんどは沢筋のゆるやかアップダウンのワインディングが続く。ハイスピードが維持できる気持ちのいい道だ。

「GTS」はこれまであった「GT」と「S」に代わるモデルで、「S」のシャシースポールがベースだ。「R70」と同じ300馬力のエンジンを搭載しているが、足回りのチューニングは日常使用を想定しながらパワーに応じたスポーティな仕立てになっている。「R70」のようなダイレクト感はないが、アニバーサリーより若干だがフットワークが俊敏だった。そのハンドリングの良さが生きたのは、試乗ルートの後半にさしかかった頃だ。
それは突然だった。道幅が一気に狭くなり、コーナーもタイトになるとこちらもスイッチが入った。ドライブモードをスポーツに切り替えるがシフトパドルは使わない。シフトアップもダウンもクルマ任せにしたが、これがドンピシャリで、右に左にステアリング操作に集中して走るワインディングが楽しくて仕方がない。とにかく直線が少ない。2速で引っ張って3速に入ったかと思うとすぐに次のコーナーが現れる。荒れた路面に落ち葉が積もる道をアルピーヌが疾駆する。ミラーで振り返ると盛大に赤い花びらのように落ち葉が舞い上がっていた。

ああ、「A110」が喜んでいる。そう感じたときだ。かつてフランスのコルシカ島でツール・ド・コルスのコースを走ったときのことを突然思い出した。ドライブしていたのはランチア・フルビアのファラローネだったが、1万のコーナーがあると呼ばれた屈指のラリーコースを、無心でステアリングを回し続けて走り切ったときの喜びは格別だった。

不思議なことに、「A110」で名前もない試乗コースを走りながら、コルシカ島の名コースを走ったときと同じ喜びを感じていた。長野の山の中にあるこんな荒れたタイトなワインディングに、大排気量のスーパースポーツを持ち込んでも決して楽しくはないだろう。しかし、小さなスポーツカーの「A110」の軽さと瞬時に向きが変わる切れ味の鋭いハンドリングは、こういう道でこそ生きる。走り終えて感じたのは、「A110」は間違いなくワインディングロードを愛するドライバーのためのスポーツカーだということだった。

最後にビッグニュースをお伝へしてリポートを終わりにしよう。11月27日、現行アルピーヌ「A110」の日本オリジナルの最終限定車「BLUE ALPINE EDITION」の発売が発表され、その受注が開始された。打ち分けは「A110」が30台、「A110GTS」が30台、「A110R70」が10台の計70台だ。正真正銘、これがアルピーヌ「A110」が新車で買える最後のチャンスになる。
休日の朝早く、「A110」でいつものワインディングロードを目指す。これほどウキウキする瞬間はない。それだけでもオーナーになる価値があるというものだ。
文/塩澤則浩 撮影/望月浩彦

Recommended






Ranking





Brands
Alpine

BMW

Lexus

Audi

Aston Martin

Cadillac

Chevrolet

Jaguar

Ferrari

Bentley

Porsche

McLaren

Maserati

Mercedes-benz

Landrover

Lamborghini

Lotus

Rolls-royce