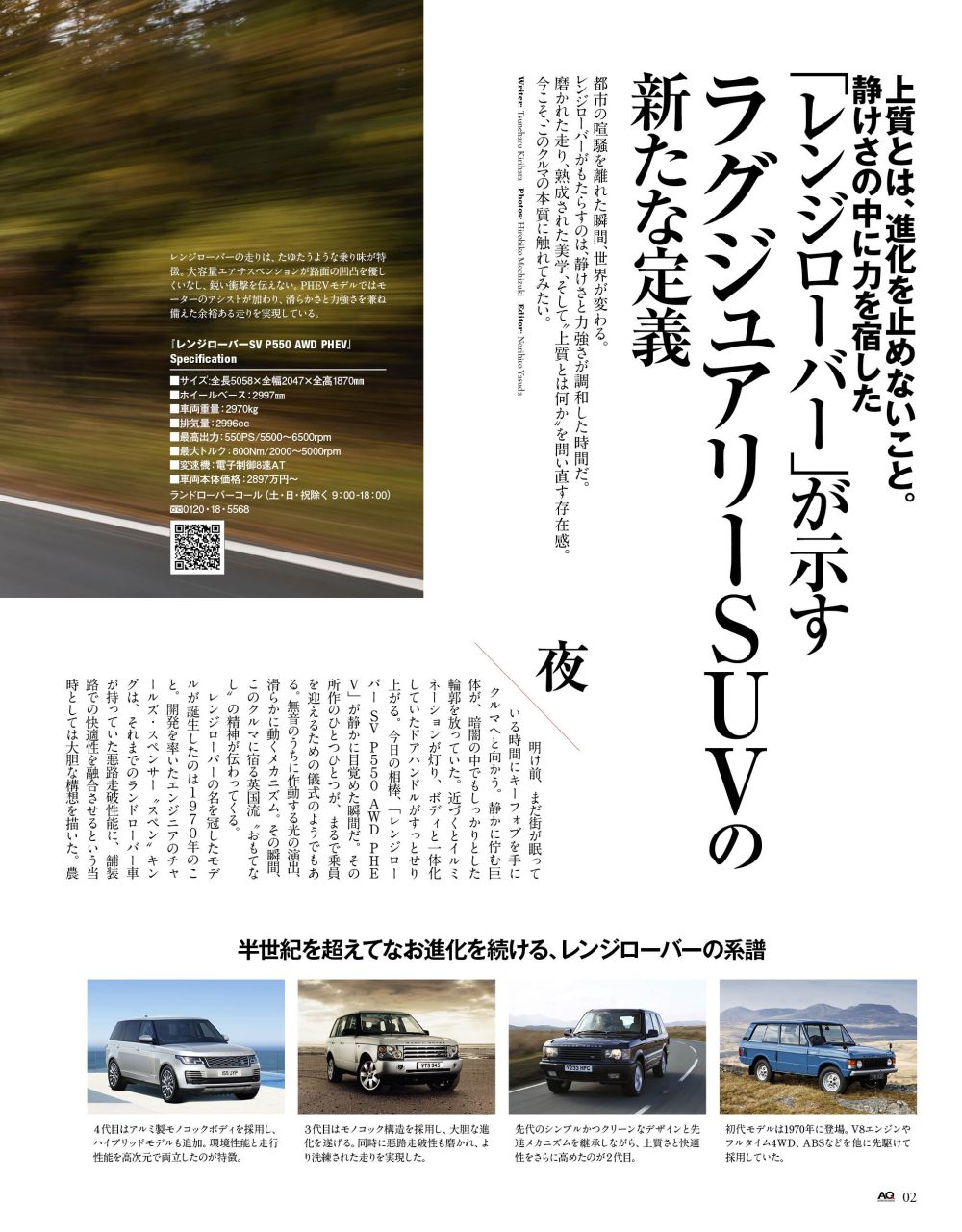日本市場に参入した英国のレーシングカーブランド「ラディカル・モータースポーツ」の正体
イギリスのレーシングカーメーカー、ラディカル・モータースポーツが、今年から日本でビジネスを本格的に展開する。千葉県南房総市の会員制ドライビングクラブ「The MAGARIGAWA Club」でメディア発表試乗会を開催した。現在、ラディカル・モータースポーツは、4種類のレーシングカーを年間約150台製造し、25か国34のディーラーで販売している。1997年の創業以来の製造台数は、約3000台以上にものぼる。


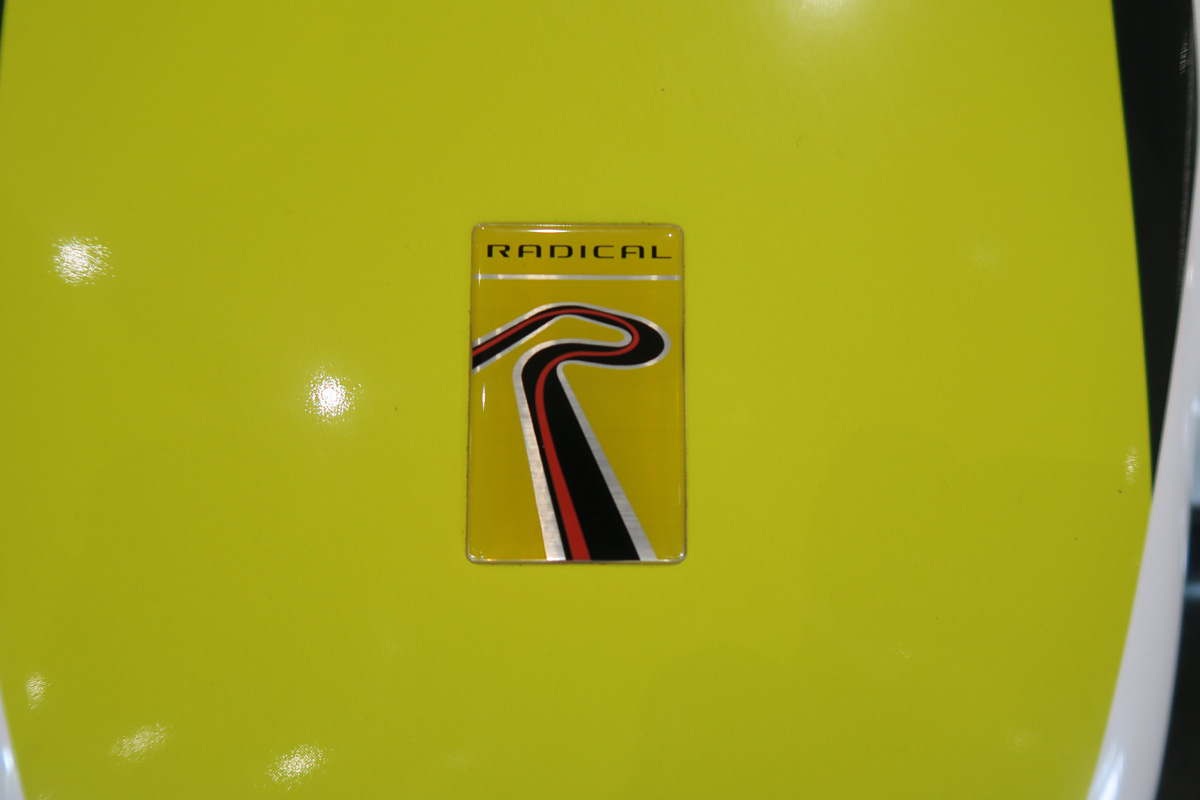
構造はレーシングカーそのもの、超高性能を予感させる
日本に導入する「SR3 XXR」は1名ないし2名乗り。カウルを外すと、強固なフレームにエンジンが組み付けられているのが見える。レーシングカーそのものの構造だ。マシンの中央部に1500ccの「RPE」(ラディカル・パフォーマンス・エンジンズ)による自社開発のエンジンを搭載。このエンジンは、スズキの大型バイク「隼」をベースに開発され、最高出力232馬力を発生する。車体重量は620kgという超軽量なので、パワーウエイトレシオは350馬力/トン以上に上り、超高性能を予感させる。



駆動系には6速シーケンシャル・マニュアル・トランスミッション(パドルシフトおよびオートブリッパー付き)が採用されている。ルマン24時間レースなどを戦うレーシングマシン「LMPカー」に着想を得た「シャークフィン」形状のセンターテールや各種のカーボンファイバー製ボディパーツなどのオプションも豊富に用意されているので、乗り方や楽しみ方に合わせたマシンに組み上げていくことも可能だ。


ヘルメットをかぶって長袖シャツを羽織り「SR3 XXR」に乗り込む。ドアはなく、ボディ開口部は狭いので、スタッフが用意してくれた踏み台に登らないと乗り込めない。シートはレース用のものなので、座面は小さく、背もたれも固定式。傾斜角度は大きくなく、6点式シートベルトで身体がキツく固定される。

もちろん、自分自身ではできないので、スタッフに締め付けてもらった。シート座面に近いところの床に消化器が固定されているので、その左端の部分を足で蹴ったりしないようアドバイスを受けて準備完了。運転席には、レーシングドライバー田中哲也氏。彼の運転でコースを3周する。


「このコースはコーナーが連続して、アップダウンも激しいので気持ち悪くなってしまう人もいます」


田中さんは優しくアドバイスしてくれたが、もし僕がそうなってしまったら手遅れだろう。ピットとなる建物を出てコースに入る。スピードを上げていくと、下向きの気流の力(ダウンフォース)によって路面にグッと押し付けられるのがわかる。

コーナー手前での減速距離も短く、6点式シートベルトが身体に食い込んでくるほどだ。もし自分が普通のクルマでここを走ったらと、違いを想定したが、すべてが違っていた。こんな短い間に高速に達しないだろうし、反対にそのスピードをこんなに短い距離で減速を完了させることもできない。

次々と迫り来るコーナーに猛スピードで侵入しながら短時間で激しく減速し、右に左に回っていく。コーナリング中もダウンフォースが効き続け、怖しいほどの速さで曲がっていく。各コーナーの頂の部分にはアラートのための細かな段差が連続して設けられている。タイヤがそれに当たると、ダダダダダダッという音とショックが伝わってくる。そこからダウンフォースが漏れてタイヤのグリップが失われた挙句にスピンしたりはしないのだろうか、と余計な心配もしながら揺すられ続けた。

ずっと路面に張り付くように走っているから、ジェットコースターのような怖さとは違うが、身体への負担は大きかった。自分で運転していないので、次にどんな反応を示すのかと、恐怖混じりで身構え続けた3周だった。これでは、吐き気を催す人が現れても不思議ではない。でも、自分で運転して、タイムを縮めていく快感に目覚めてしまう人もいるだろう。まさしくスポーツとしての快楽だ。現代のレーシングマシンの要となっているエアロダイナミクスの凄みを体感できるのが他のレーシングカーとの違いだ。

エクストリームなクルマの楽しみ方を提案
「SR3 XXR」のベース車両本体価格は2158万9000円だが、各種オプションを組み込んでいくと3000万円近くになってしまうのではとスタッフが語っていた。アジア圏では、すでにオーストラリア、中国、フィリピン各国でラディカルは販売されている。日本でも販売を開始し、2026年にはこのクルマだけでのレースシリーズ「ラディカルカップ」を開催することが目標だそうだ。そのためには、「最低でも15台が必要」(本社の事業開発マネージャー、クリス・プルーデン氏)とのこと。

風光明媚なところをドライブがてら訪れる、旧車を所有し自分でメインテナンスする、あるいはイベントに参加するなど、クルマの楽しみ方にはいろいろある。それらの中でも、ラディカルを買ってコースで走り込み、やがてはレースに参戦するというのは、間違いなくエクストリームなクルマの楽しみ方のひとつだろう。資金も時間も人手も必要となるが、ラディカルでなければ体得できない喜びと楽しみが存在しているはずだ。

■関連情報
https://www.radicaljapan.co.jp/
文/金子浩久
Recommended






Ranking





Brands
Alpine

BMW

Lexus

Audi

Aston Martin

Cadillac

Chevrolet

Jaguar

Ferrari

Bentley

Porsche

McLaren

Maserati

Mercedes-benz

Landrover

Lamborghini

Lotus

Rolls-royce